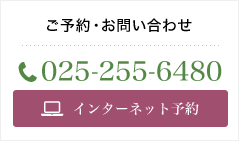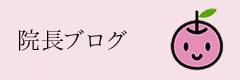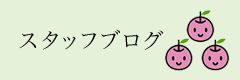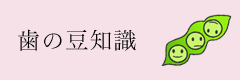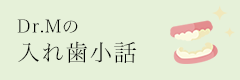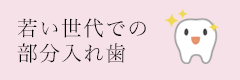歯の豆知識
歯の豆知識 バックナンバー
入れ歯での食べ方は・・・
左右両側で同時に噛むようにしましょう
総入れ歯の場合、前歯と左右の奥歯をバランスよく使って噛むことが重要です。例えば右側だけで噛むと下顎総入れ歯の左側が浮いてしまい、安定して噛めなくなります。左右両側で均等に噛むことにより、歯肉が軽い圧力に慣れていきます。
また前歯だけで噛まないようにしましょう。入れ歯の後方部から空気が入り陰圧が保てなくなり、入れ歯が外れやすくなりますからね。
入れ歯で食べることに慣れたら、硬めの果物や肉など、硬い食べ物にも挑戦してみてください。
最初は柔らかい食べ物で慣らす
新しい入れ歯の場合、
– 卵
– 魚
– 調理した野菜
– アイスクリーム
このような柔らかい食べ物を食べてみましょう。
これらの食べ物は、噛んでいるときお口に大きな負担がかかりません。
サイズを小さめにして調理する
上下総入れ歯の場合の咀嚼能率は、上下28本の歯がそろっている場合に比べて25~30%ほどです。つまり上下総入れ歯にすると、歯がそろっていたときと比べて噛む力が4分の1程度まで落ちてしまいます。そのため、食べ方にも工夫が必要です。一度にたくさんのものを口に入れず、少しずつわけて口に入れるようにしましょう。
そして、噛みやすい一口サイズの大きさにして調理しましょう。肉のような弾力のある食べ物、繊維の多い野菜などは長時間煮込んだり蒸したりして柔らかくして食べましょう。
慣れるように努力しましょう
新しい入れ歯に慣れるまでの間、食習慣を調整するようにしましょう。かなり柔らかい食べ物から試すとよいでしょう。また、お口が入れ歯装着の感覚に慣れるまで、最初の数週間は硬い食べ物や噛みきりにくい食べ物は避けた方がよいです。ステーキ、フランスパン、ナッツ、硬いキャンディーは、咀嚼が問題なくできるようになるまで避けてください。
初めて硬い食べ物に挑戦するときは、小さな一口サイズに切って噛みやすくしてください。硬い食べ物は飲み物と一緒に食べるとさらに噛みやすくなります。
ゆっくり時間をかけて入れ歯に慣れていき、食事のときには自分のペースで新しい食べ物に挑戦していきましょう。
大切なのは最初から、何でも食べられるとは思わないことです。そして、少々難儀であったとしても、諦めないことも大切ですよ。
皆、リハビリして努力した結果、入れ歯でも食べるようになったんだということを認識しましょう。
歯周病と糖尿病との深い関係
糖尿病は歯周病と深い関係があり、糖尿病があると歯周病の発症率が健康な場合と比べて2.6倍になるという報告があります。更に歯周病は糖尿病を悪化させることも解っています。
これは歯周病で生じた炎症によって分泌されたサイトカインが血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きを抑制するためです。インスリンの働きが抑制されると血糖値が上昇し、糖尿病が悪化します。
さらに、血糖値が高い状態では免疫の働きが低下するため、歯周病菌が増殖し、炎症が起こりやすい状態になります。
つまり、糖尿病がある場合に歯周病をそのままにすると、糖尿病が悪化し、それを受けて歯周病も悪化するという悪循環に陥るのです。
そのため、糖尿病で内科に罹られている方は、一度、歯科医院にも行って歯科健診を受けるようにしましょう。
骨隆起を知っていますか?
歯科診療をしていると、歯茎の腫れを主訴に来院される患者さんが多くいます。
その中で上顎の中央や下顎の内側にできたコブのような腫れを心配し、受診される方がいます。それらのほとんどは、「骨隆起」と呼ばれる非腫瘍性の骨の隆起で、骨質の局所的な過剰発育です。
この原因は明らかではありませんが、炎症性刺激や歯を介して顎骨に加わる咀嚼応力などの咬合機能が関与していると言われています。
実際に臨床上では目にすることが多く、歯ぎしりや喰いしばりが強い方によく見られますが、遺伝的な可能性もあります。
骨隆起は骨の膨らみのため、触ると「硬い」感じがします。
骨隆起は、その存在自体が問題になることは少なく、経過観察することが多いのですが、大きさや形状によっては入れ歯の製作や装着の際に障害となったり、口腔清掃が困難で炎症を引き起こしたりする問題があります。
また、それらの隆起を覆う粘膜は薄いため、硬い食物の接触刺激で痛みや潰瘍を認めることもあります。もし障害が出るようであれば、骨隆起を切除する外科手術を行われることもありますね。
妊娠中は歯周病になりやすいのです
女性ホルモンが変化すると歯茎が炎症を起こしやすくなることが知られています。
歯周病菌の中には、女性ホルモンを餌として繁殖するものがあります。出産前の女性ホルモンの分泌量は月経時の10~30倍。
そのようなことからも、妊婦は歯周病になりやすいといえます。
歯茎が炎症を起こすと、歯茎が腫れると歯との間の溝も深くなり、歯垢が溜まります。歯垢に含まれる歯周病菌により歯茎が炎症を起こし、さらに溝が深まって「歯周ポケット」になります。
そしてこれは歯ぎしりなどの過剰な咬合力がかかることでより進行いたします。
空気を嫌う歯周病菌がそこで繁殖して微弱な酸を作り出し。歯を支える骨まで溶かします。
妊婦が歯周病の場合、早産や低出生体重児のリスクが高まるという調査結果があります。それは喫煙や高齢出産よりも高いと言われています。
なぜなら子宮を収縮させて出産を促す物質が歯周病菌による炎症からも生じ、歯茎から血管に入り早産に繋がることがあると考えられています。
また歯周病になると血糖値が上がるともいわれ、妊娠糖尿病の人はより注意が必要です。
妊娠中の歯周病治療は応急処置になってしまうことが多いです。
そのため、日ごろから口内を清潔にしておく必要があります。
できれば妊娠前からの定期健診を歯科医院でしっかり受けて、歯磨きのチェックをしてもらうように心がけましょう。